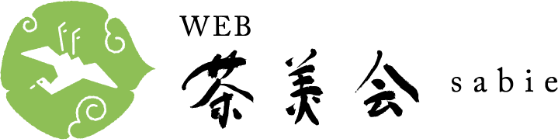倉知可英さん演出に冴え
ダンスとピアノで綴る「白昼夢」
裸足で戯れる秘密の花園
世紀末パリを舞台に花開いたベル・エポック(良き時代)。この時代に活躍した、光と色彩の作曲家ドビュッシー。耳に馴染むメロディーながら、それでいてちょっとへそ曲がりなサティ。親交を結んだ2人の音楽10曲余を中心に、ダンスとピアノの掛け合いで綴る白昼夢の世界が展開しました。名古屋市を拠点にする現代舞踊家、倉知可英(かえ)さんとピアニストの山内敦子さんが2022年9月23日、名古屋市千種区文化小劇場(千種座)で開いた公演「白昼夢への誘い jardin secret 秘密の庭」です。
白昼夢をモチーフに、ピアノなど鍵盤楽器による演奏とダンスが組み合わされた組曲風の構成です。サティの「ヴェクサシオン(嫌がらせ)」という短い曲を、前奏曲あるいは間奏曲、終曲として繰り返し奏で場面をつなぐ。ムソルグスキーの「展覧会の絵」のように、ドビュッシーとサティの音楽世界に誘われ、彼女たちが裸足で戯れ、遊ぶ、"秘密の花園"を見ていくようです。
ヴェクサシオンのピアノによる前奏に続いて、ドビュッシーの「水の反映」が演奏されます。舞台奥に吊るされたスクリーンのような薄い白布越しに、倉知さんの踊る様子が影絵のように映し出されます。人影は二重、時に三重にも見えて、曲名の「水に映る影」ならぬ白布に映る舞踊像が、美しくも幻想的です。
この場面の冒頭、倉知さんはバレエ「白鳥の湖」のオデット姫が見せる白鳥の羽の動きを、手振りで影絵風に見せます。バレリーナのような踊りを見せた後、次第にバレエの束縛から解き放たれ、感情のままに自由に踊ってゆきます。白布の向こうで踊っていた倉知さんは、曲が終わると白布の下をくぐって、裸足でステージに登場しました。
このシーンは、モダンダンス(現代舞踊)の祖として知られるアメリカの舞踊家イサドラ・ダンカン(1877-1927年)へのオマージュなのでしょうか。ダンカンは幼い頃から古典バレエを学ぶも飽き足らず、やがて「自然に帰れ」をモットーに、感情のおもむくままに踊る「自由なダンス」を創出しました。1900年、パリ万博の年、フランスで初公演しました。バレエ・シューズやタイツを脱ぎ捨て、自由に、自然に人間を賛美して踊る「裸足のイサドラ」は、サロン文化が花開いたパリで、芸術家や知識人を魅了しました。ドビュッシーやサティと同時代に活躍した舞踊家です。
このシーンに、倉知さんの演出の冴えと芸術史への造詣、先人への敬愛の程が凝縮されているようでした。

ダンサーとピアニストの共演というと、ピアニストは演奏に徹し、せいぜい座ったまま弾き続けるピアニストにダンサーが絡むのが常ですが、本公演は2人の掛け合い、パフォーミングアーツを両者で構築してゆく姿勢が徹底されていました。
グランドピアノをミニチュア化した「トイピアノ」を巡って、ヴェクサシオンを奏でる山内さんと鬼ごっこするようなシーン。2人がトイピアノを巡って、子犬が戯れ合うような様はメルヘンのよう。鍵盤ハーモニカも効果的に使われました。
倉知さんがはじめは仰向けになりながら歌ったドビュッシーの歌曲「美しき夕べ」では、舞台奥の白布は、歌詞の字幕スクリーンとなり、翻訳された歌詞があたかも踊るように投影されました。歌とピアノ、映像が絡み合って、白昼夢の世界です。
終盤、スカートを鐘型に張らせるフレーム付きの衣装を着用した2人はレトロな一対の人形のよう。倉知さんは紡錘状のフレームを伸縮したり、着脱したり、まくし上げて被ったり。衣装が何通りにも見えて、アイデアものです。
作曲家大河内俊則さんがドビュッシー、サティへのオマージュとして作曲依頼を受けて初演された「run around in circles」(堂々巡りの意)では、作曲家自身が映像操作。ピアノの上、客席の左右前方からの計3台のカメラが撮影するライブ映像が、白布のスクリーンにモノクロで投影されました。特殊なエフェクトにより、ダンサーとピアニストの動きが微妙にずれて、合成映像のような不思議な効果を発します。
新作に続いて、終曲となるヴェクサシオンの場面では、映像は画素が次第に粗くなって無機質化し粒子になってしまう。そして、スクリーンを剥ぎ取るような場面で、舞台は暗転してラストになりました。
テクノロジーの進化によって人間の営みがデジタル化、無機質化してゆく現代に対する音楽とパフォーマンスによる「ヴェクサシオン」。そんな意味が込められているのでしょうか。白昼夢からの"目覚め"は、なかなか意味深でした。
倉知さんのダンスは音に反応して、手足、体全体を自在に激しく動かす即興風の踊りが多く、最初は新鮮に映っていましたが、内からわきおこるダンスの芯になるものが、なかなか香り立ってきません。音に即しつつ、音楽からあえて脱却する試みなのでしょうか。
実験的な舞台の演出に才を発揮しつつ、その上で踊りを磨く。企画・演出・主演すべてをこなす舞踊家が、自身の踊りをどう客観視するか。難しい課題だと思いました。
ドビュッシーやサティをニュアンス豊かに演奏する難しさも感じた舞台でした。
=WEB茶美会編集長・長谷義隆