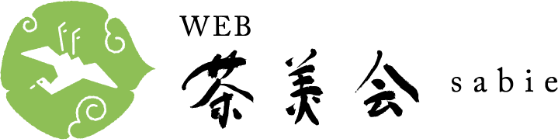一器・一花・一菓
〜古赤絵の仙盞瓶 〜
「花いらず」生けてこそ
紅白の梅と有楽椿を
「今回は"花いらず"です」。ある年の徳川美術館主催の「徳川茶会」の濃茶席は、茶花がない異例の床の間でした。担当の学芸員は、花がなくてもこの床の間の室礼は格調高いでしょう、と言わんばりの顔つきでした。花入は、赤絵に金彩を施した中国・明時代の華やかな 金襴手唐子文仙盞瓶(せいさんぴん)。
「花いらず、ですか。この花器なら、はあ、ごもっとも」と感じつつ、一方で「おいおい、そう居直らずに、そこに映える花を生けるのがお茶ではないのか」と突っ込みたくなりました。そんな割り切れない思い出は、何年経って消えないもの。仙盞瓶を見るとよみがえってきます。
仙盞瓶は、ペルシャの銀器を模して作られた陶器製の水注で、盛盞瓶とも洗盞瓶とも書かれます。 胴の形は様々ありますが、注ぎ口や持ち手が細く華奢に作られているのが特徴です。日本では江戸時代の萬古焼の写しが知られています。

「花いらず」で思い出すのが、重要文化財指定の古伊賀花生、銘「芙蓉」です。個人所有で滅多に見る機会がなく、2004年の名古屋美術倶楽部創立百周年記念展に出品され、食い入るように見て、目に焼き付けました。松平不昧公出入りという関西屈指の茶道具商「谷松屋戸田商店」の当主戸田鍾之助さんが、顧客の数奇者とおぼしい紳士に、「これが有名な、別称花いらずの伊賀です」などと、解説。それを脇で漏れ聞いて、花いらずという茶道用語があるのを知りました。かの鈍翁の弟、益田紅艶が手に入れて内箱蓋裏に「この伊賀に上野あるかは志らねども花は不用と人は云ふなり」と狂歌を添え、不用に芙蓉をかけて、平たくいえば親父ギャグですが、しゃれた銘を付けたものです。焦げと萌黄色のビードロ釉がたまらない名品です。
景色満点のゴリゴリした伊賀焼ほど、実は花映りがいいのです。存在感満点の花器を生かす工夫するのが茶人の楽しみであり、苦しみでもあるのでしょう。

果報は寝て待て。美術館ピースであるはずの仙盞瓶が先年、なんと、ある古美術の入札会に出品されたのです。埃をかぶって薄汚れていましたが、釉肌の白さ、上絵の調子、古赤絵らしい朱色、そして注ぎ口や持ち手の華奢な造形の見事さ。金欄手ではないものの、むしろ茶味があるのも好ましく、明時代の作と確信。応札したところ、めでたく落札しました。踏んだ通り、汚れを落としたら、本来の輝きがよみがえりました。
満を持して、先日拾穂園で催した四季の茶の湯梅花祭編で、薄茶の花入として使いました。徳川茶会のように「花いらず」は、いただけません。梅花を主題としたこの日の取り合わせでは、梅は欠かせません。金彩こそありませんが、華やかな古赤絵の仙盞瓶は、徳川美術館所蔵の仙盞瓶と同工異曲の作品。余白の美が決めて思い、ぐっと伸びた枝の先に数輪の蕾と僅かに花を残した紅梅を中心に据え、白梅の枝と薄紅の有楽椿を楚々と投げ入れました。
最初は、真横に置いてみましたが、面白からず。器を45度左に振って、注ぎ口を客付けに向けると、動きが出て、造形性・装飾性もより感じられ、茶味が出たたようです。
口いっぱいまで水を入れたら、細い注ぎ口から水が溢れ出てきました。お飾りの造形ではないんだ! 水注本来の機能を持っていることに、驚かされました。いつか、水次やかんの代わりに、仙盞瓶を使おうかしらん。でも、ちょっとこわいな。大寄せ茶会では無理でも、茶事なら濃茶は水次、薄茶は花入に見立てるのも、一興かもしれません。