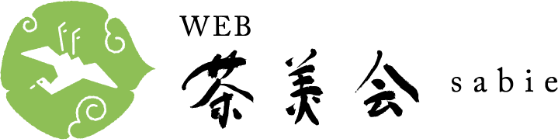一器・一花・一菓
薄紅絞り染め
木槿の蕾 伊賀蹲に
咲き初めの花に会うと、心がときめきます。巡る季節、今年もこの花に再び会えた。そんな喜びが湧きます。
先がけの花を床に飾ることは、茶人にとって何よりのご馳走です。
風炉を代表する茶花、木槿(むくげ)の蕾が、ふくらんできました。もう明日朝には咲くか、という風情の底紅の一枝を今朝切って、蹲(うずくまる)の花入に投げ入れました。
薄紅を白生地に絞り染めしたよう。自然が染めた儚い美しさです。朝咲いて夕方と言わず、昼下がりにはしぼむ木槿。一日花の初咲きを愛でる、思えばなんと特別な味わいでしょう。

花器の蹲とは、人間ががうずくまった姿に似るところからの名前です。信楽や伊賀の種壺の小振りなのを、花入に見立てたのが茶人の功。壁床の中釘や、小間の床柱に掛けると、最も映りがよく、拾穂園では好んで田舎家風の茶室の壁床に掛けて、季節折々の花を投げ入れて楽しんでいます。

古来「伊賀に掛けなし、信楽に掛けあり」といわれますが、この伊賀焼は現代作家・谷本景さんのもの。種壺形の素直な器形。前面にひとヘラ入れて作為を見せます。作家の作為を超えるように、激しい炎が生んだ変化に富む景色は、見るたび新鮮です。使い飽きしません。
茶道具の取り合わせの上で、古作は味わい深く、伝世の風格、故人への敬慕を表して好ましいのですが、やはり古作一辺倒は避けたいもの。古物礼賛、懐古趣味に陥らず、茶席の取り合わせには同時代への共感、眼差しがありたい、と。茶の湯の祖・珠光の言葉を借りれば。和漢の境のみならず、古今の境を取り紛らわすよう、心を配りたいものです。