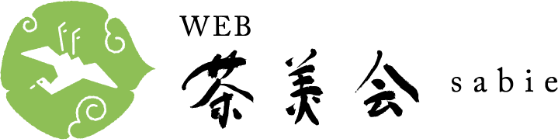一器・一花・一菓
壺飾り後、茶壺を花入に
古唐津の四耳壺
大胆な発想で模様替え
濃茶と薄茶の二服点てる茶会において、どう劇的に場面転換するか。拾穂園で先日催した茶会で、ささやかな試みをしました。初座の濃茶では床の間に壺飾りした茶壺を、後座では壺を覆っていた網、口覆いを取り外し、花入に見立てたのです。
控えの間から改めて席入りしたお客から「わあ」という嘆声があがるのが、障子越しに聞こえました。目の肥えた方々の好反応。亭主冥利に尽きる瞬間です。

かつては、といっても信長、秀吉の時代ではありますが、茶道具の第一と珍重された茶壺。時は移り茶入、さらに茶碗へと、その座はとって代わられたとはいえ、茶壺の格式は今も受け継がれ、花入に見立てるのは、少し勇気が要りました。
どの茶壺でも、花映りがいい花入になるか、と言うと、そうでもありません。ルソンの真壺では、格調が高すぎて、どうもそぐわない。壺飾り稽古用の新出来の茶壺では、一人二役はそもそも無理です。
そこで選んだのが、伊羅保釉がかかった古唐津の四耳壺です。花をより美しく見せるには、色彩が競合しない控えめな古唐津が似合います。茶壺といえば、ルソンか古瀬戸が定番です。そこへ古唐津。しかも唐津では珍しい伊羅保釉という意外さもごちそうです。古唐津によくある素朴一徹ではなく、口造り、耳とも剛健にして精作な大壺です。
茶席は小間。寄付から露地口の木戸を開けて、茶庭の踏み石を伝って小間席へにじり口から席入りしたお客は、薄明かりの床の間に飾られた茶壺を見ます。
壺は蓋をしてその蓋と口にかけて封をし、口覆いを菱なりにかけます。そしてその口覆の上から口緒で結んで壺を網に入れ、網の緒を結んで初座の床に飾っておきます。なかなかに荘厳です。
古筆切の掛け軸がかかった床の間に、重厚な茶壺。口切りの趣向がいや増します。茶壺拝見の所望があるかと用意してましたが、遠慮深いのか、残念。ありませんでした。

後座の薄茶は一点して席中は明るくし、それまではっきり見えなかった茶釜の地紋もくっきり。古筆の筆者、藤原定家にちなんだ地紋が浮き上がり、しばし、釜拝見の時が流れました。陰から陽へ、茶席はすっかり雰囲気が変わります。さらに一つサプライズを仕込みました。それが、茶壺を花入に転用するという趣向でした。
茶花は、2種類の組み合わせを用意しました。
咲き初めた薄紅の椿(関戸太郎庵)に晩秋の風情を醸す照り葉(まんさく)。
もう一つは、椿はそのまま、緑の葉の生命力を基調に、朱の実が鮮やかなセンリョウとの組み合わせです。
ころは錦秋も終わりがけ。里の紅葉も、はや散りかかっています。拾穂園の茶庭の楓やドウダンツツジの葉も赤く燃えています。いまさら茶席に照り葉をいけても、自然の景色にはかなわない。そう考えて、葉が散りゆく物寂しい晩秋にこそ、新たな生命力がみなぎる取り合わせを、と後者を選択しました。